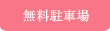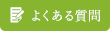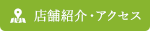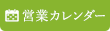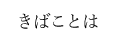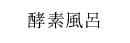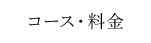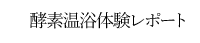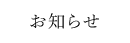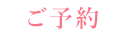カテゴリ
- もう、がんでは死なない (32)
- このクスリがボケを生む! (30)
- 口臭 (1)
- 47の心得 (77)
- アレルギー (4)
- 便 (13)
- 自律神経 (27)
- 運動 (24)
- メタボリックシンドローム (6)
- 体温 (42)
- 血液 (22)
- ストレス (41)
- 呼吸 (5)
- 酵素風呂きばこ案内 (53)
- ファスティング (6)
- 酵素風呂の記事 (10)
- 酵素栄養学 (79)
- 白湯 (8)
- 酵素とは? (11)
- 汗 (23)
- 酵素風呂 (54)
- 冷え (62)
- ダイエット (7)
- ゲルマニウム温浴 (7)
- プレ更年期1年生 (40)
- 医者が患者に教えない病気の真実 (57)
- 更年期に効く美女ヂカラ (26)
- 食品の裏側 (51)
月別 アーカイブ
- 2026年1月 (4)
- 2025年12月 (5)
- 2025年11月 (4)
- 2025年10月 (4)
- 2025年9月 (5)
- 2025年8月 (4)
- 2025年7月 (4)
- 2025年6月 (5)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (4)
- 2025年3月 (5)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (5)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (4)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (4)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (5)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (5)
- 2022年9月 (5)
- 2022年8月 (5)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (5)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (4)
- 2021年11月 (5)
- 2021年10月 (4)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (5)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (5)
- 2021年5月 (6)
- 2021年4月 (6)
- 2021年3月 (6)
- 2021年2月 (5)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (5)
- 2020年9月 (6)
- 2020年8月 (7)
- 2020年7月 (6)
- 2020年6月 (7)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (7)
- 2020年3月 (6)
- 2020年2月 (6)
- 2020年1月 (6)
- 2019年12月 (7)
- 2019年11月 (6)
- 2019年10月 (6)
- 2019年9月 (7)
- 2019年8月 (6)
- 2019年7月 (7)
- 2019年6月 (6)
- 2019年5月 (6)
- 2019年4月 (7)
- 2019年3月 (7)
- 2019年2月 (6)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (6)
- 2018年11月 (4)
- 2018年10月 (5)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (4)
- 2018年7月 (5)
- 2018年6月 (4)
- 2018年5月 (4)
- 2018年4月 (5)
- 2018年3月 (4)
- 2018年2月 (4)
- 2018年1月 (5)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (4)
- 2017年10月 (4)
- 2017年9月 (4)
- 2017年8月 (4)
- 2017年7月 (5)
- 2017年6月 (8)
- 2017年5月 (11)
- 2017年4月 (11)
- 2017年3月 (6)
- 2017年2月 (7)
- 2017年1月 (13)
- 2016年12月 (9)
- 2016年11月 (11)
- 2016年10月 (9)
- 2016年9月 (10)
- 2016年8月 (11)
- 2016年7月 (19)
- 2016年6月 (21)
- 2016年5月 (14)
- 2016年4月 (6)
- 2016年3月 (1)
最近のエントリー
ブログ 2ページ目
倦怠感・疲れやすさ
更年期症状で多くの人が感じるものの1つが「疲れやすさ」や「倦怠感」
「やる気の喪失」です。
これは、女性ホルモンの分泌低下による自律神経の乱れが大きな原因です。
一時的な疲れであれば、休息を取れば回復しますが、更年期の疲れはなかなか回復せず
回復したと思ってもまたすぐに疲労感がやってくるのが特徴です。
そして、「今まで普通にできていたことができなくなった」
「やるべきことができなかった」などと自分を責めてしまいがちですが
ここで大切なことは「この時期は疲れやすくて当たり前」
「普段よりできなくても大丈夫」と割り切り、無理をしないということ。
何でも自分でやろうとせず、家族や周りの人を頼ることで精神的な安定に繋がってきます。
<参考書籍>
更年期に効く美女ヂカラ(リベラル社・2023)
著者:高尾美穂
【 きばこより一言 】
酵素風呂の入酵により、血流改善することで
自律神経が整えられますので、疲労感解消に繋がります。
(きばこ酵素風呂) 2025年11月17日 14:08
更年期と向き合う時間を作る
更年期症状には、ホットフラッシュや多汗などのようにわかりやすいものもあれば
「仕事上のミスが増えた」「今までできていたことが出来ない」「集中出来ない」などといった
日常生活でのちょっとした変化もあります。
そんな更年期をネガティブに捉えすぎず、自分の身体と向き合う時間を作ることが大切です。
更年期は人生において「曲がり角」といえる時期。
これまで100%の力で頑張ってきた人も、ここで一度スピードを落とすことで、この先の人生も
健康に明るく過ごすことができるはずです。
そのため、仕事や生活などのボリュームを抑え、自分の身体と向き合う時間を作りましょう。
また、更年期や閉経に対してネガティブなイメージを持ちすぎず
ありのままの自分を受け入れてみてください。
<参考書籍>
更年期に効く美女ヂカラ(リベラル社・2023)
著者:高尾美穂
【 きばこより一言 】
身体を芯から温め血流改善と酵素補給のできる酵素風呂は
健康で明るく過ごす為のお手伝いツールに最適です!
実は一番に冷えを溜めてしまう夏の季節
汗をかく量が減り、悪い汗の原因を作ってしまう冬の季節
知らず知らずの内に溜めがちな日常の疲労とストレスを
是非、定期的に酵素風呂入酵で調整して
自分の身体と向き合う時間作りをしてみて下さい!
(きばこ酵素風呂) 2025年11月10日 17:08
更年期に起こる代表的な不調
今回は「更年期に起こる代表的な不調」というテーマです。
更年期には心身に様々な不調が現れます。
ときには複数の症状が重なったり、日によって症状が異なることもあります。
そんな不調の例を挙げていきます。
①ホットフラッシュ、多汗:身体が突然カーッと熱くなる、汗が止まらなかったりする
②倦怠感:やる気が起こらなかったり、すぐに疲れてしまう、集中力がなくなる
③眩暈:「天井や景色がぐるぐる回る」、「身体がフワフワして足が地につかないような感じがする」
「目の前が暗くなり、気が遠くなるように感じる」などの眩暈がある
④イライラ:ちょっとしたことで不安になったり、怒りっぽくなったりと感情の起伏が激しくなる
⑤頭痛:片頭痛、頭全体が重い、うなじが痛いなど、症状は様々。
吐き気を伴うほどひどくなることも
⑥動悸、息切れ:激しい運動をしたわけでもないのに、急に心臓がドキドキしたり
息が苦しくなったりする
⑦首・肩こり、腰痛:更年期になり、肩こりが酷くなったり、手指の関節に痛みが出たりすることも
腰痛はヘルニアや腰椎すべり症などの病気の可能性も
<参考書籍>更年期に効く美女ヂカラ(リベラル社・2023)
著者:高尾美穂
【 きばこより一言 】
酵素風呂入酵により、身体を芯から温めて血流を良くし
身体全体から酵素を取り入れる事で
上の症状の改善が期待できます!
ぜひ一度酵素風呂を体験してみて下さい。
(きばこ酵素風呂) 2025年11月 3日 20:54
更年期症状と間違えやすい病気
今回は「更年期症状と間違えやすい病気」というテーマです
更年期に起こる不調は身体的なものから精神的なものまで多種多様です
<甲状腺の病気>●機能亢進:異常発汗、動悸、のぼせ、痩せる
●機能低下:冷え、無気力、倦怠感、太る
<関節リウマチ> 関節の痛みや腫れ
特に朝起きた時の関節のこわばりは関節リウマチの典型的な症状
<うつ病> 気分の落ち込み、イライラ、食欲低下。
<子宮内膜ガン> 不正出血、閉経後の出血、おりものの変化
(茶褐色など色がついている、チョコレート状など)
<メニエール病> 回転性の眩暈が10分間〜数時間続き、何度も繰り返す
難聴、耳鳴り、耳閉感(耳が詰まった感じ)を伴う
<参考書籍>
更年期に効く美女ヂカラ(リベラル社・2023)
著者:高尾美穂
【 きばこより一言 】
酵素風呂入酵により、身体を芯から温めて血流を良くし
身体全体から酵素を取り入れる事で
上の症状の改善が期待できます!
ぜひ一度酵素風呂を体験してみて下さい。
(きばこ酵素風呂) 2025年10月27日 16:19
女性に多い甲状腺の病気
更年期症状だと思っていたら、別の病気だったということがあります。
代表例が甲状腺の病気です。
甲状腺は喉仏のすぐ下にあり、蝶が羽を広げたような形をしています。
甲状腺から分泌される「甲状腺ホルモン」には、筋肉の維持や新陳代謝の促進
体温調節など身体の代謝を調整する様々な役割があります。
そして、この甲状腺ホルモンが過剰になる病気の1つが「バセドウ病」であり
息切れや動悸、異常発汗やほてりなどの症状が現れます。
反対に不足するのが「橋本病」であり、無気力や気分の落ち込み
疲れやすさや肌のカサつきなどの症状が見られます。
甲状腺疾患は加齢に伴って増加し、更年期世代の女性には一般的な疾患です。
更年期障害と診断するためには、甲状腺疾患の除外が必須です。
<参考書籍>
更年期に効く美女ヂカラ(リベラル社・2023)
著者:高尾美穂
【 きばこより一言 】
人が年齢を重ねていく内には
老化現象として様々な病気のリスクが大きくなります。
人間の身体の健康のカギを握る酵素の働きを活発化させる為に
全身から酵素を取り入れる事のできる酵素風呂への定期入酵で
アンチエイジング効果が期待できるようになります。
(きばこ酵素風呂) 2025年10月20日 19:11
季節の変わり目に酵素風呂
10月に入り、気温や湿度も下がることで過ごしやすい時期となりました。
しかし、近年の急激な気温の変化により、体調を崩してしまっている方が大勢います。
 そんな季節の変わり目には「酵素風呂」がおすすめです。
そんな季節の変わり目には「酵素風呂」がおすすめです。
酵素風呂入酵により、代謝や免疫力を向上させて
体調不良とは無縁の生活を過ごしていきましょう。
 からの季節の変わり目に
からの季節の変わり目に酵素風呂
 の発酵熱
の発酵熱 で身体の芯を温め
で身体の芯を温め 疲労回復し
疲労回復し元気に
 過ごしましょう!
過ごしましょう!
(きばこ酵素風呂) 2025年10月13日 11:02
PMSが重い人は、更年期症状が出やすい傾向に
今回は「PMSが重い人は、更年期症状が出やすい傾向に」というテーマです。
月経が始まる3〜10日前から起こる不調をPMS(月経前症候群)といいます。
イライラや気分の落ち込み、乳房や下腹部のハリ、倦怠感など様々な症状があり
排卵後の女性ホルモン分泌の変化が原因の1つとして考えられています。
そして、PMSが強かった人は更年期症状も重くなりやすいというデータがあります。
ある調査では、PMSがなかった人を1とすると、PMSがあった人は
ホットフラッシュが2.1倍、抑うつが2.3倍リスクが高いという結果が出ています。
更年期に効く美女ヂカラ(リベラル社・2023)
著者:高尾美穂
【 きばこより一言 】
女性の身体は、特有の機能を持っておりますので
加齢による身体の変化に大きな影響を受けず
日常生活に支障なく、健康で元気に過ごす為のツールに
酵素風呂を利用して、常に酵素の自然治癒力アップを
図る事をお勧めします!
(きばこ酵素風呂) 2025年10月 6日 20:06
人それぞれの更年期症状
今回は「人それぞれの更年期症状」というテーマです。
「更年期」は全ての女性に訪れるものですが、「更年期症状」には個人差があります。
「更年期障害」と診断されるほど辛い症状に悩まされる人もいれば
何事もなく更年期を終える人もいます。
この違いには体質だけでなく、その人の置かれた環境や性格など様々な要因が
あると考えられています。
PMSや月経痛、つわりなどと同様に更年期症状も人それぞれです。
なので、「なぜ自分ばかり」と悲観せずに個性だと考えてみましょう。<参考書籍>
更年期に効く美女ヂカラ(リベラル社・2023)
著者:高尾美穂
【 きばこより一言 】
先ずは
身体の変化が著しくなっていく30代からは
日常の身体の健康を意識した生活が大切になります。
そしてその頃から
酵素風呂に最低月に一回のペースで定期入酵すれば
温浴で体内に取り入れる酵素の力で代謝(免疫力)が上がり
女性特有の大転換期や閉経後の「更年期症状」にも
不調の少ない活力のある身体を保った生活が期待できます!
(きばこ酵素風呂) 2025年9月29日 12:06
月経周期の乱れは閉経が近づくサイン
今回は「月経周期の乱れは閉経が近づくサイン」というテーマです。
閉経が近づく最もわかりやすいサインは、月経周期の乱れです。
正常な月経周期は25〜38日ですが、更年期に入ると周期が短くなったり
反対に2〜3ヶ月に1回になったりと、次の月経がいつくるのかわからなくなることが
増えてきます。
また、卵巣機能の低下でホルモン分泌が不安定になると
子宮内膜がうまく剥がれず厚くなりすぎるために、大量出血や不正出血が起こることも。
ただし、閉経までのプロセスには個人差があり、様々なケースがありえます。
<閉経前後の多種多様な症状>
●運動系症状:肩こり、腰痛、関節痛など
●血管運動神経系症状:ホットフラッシュ、動悸、冷えなど
●精神神経系症状:不眠、うつ状態、イライラなど
●消化器系症状:食欲不振、胃もたれ、便秘など
●泌尿器・生殖器系症状:月経異常、尿もれ、頻尿など
●皮膚・分泌系症状:皮膚・粘膜の乾燥、口の渇きなど
<参考書籍>
更年期に効く美女ヂカラ(リベラル社・2023)
著者:高尾美穂
【 きばこより一言 】
酵素風呂入酵により、身体を芯から温めて血流を良くし
身体全体から酵素を取り入れる事で
上の症状の改善が期待できます!
ぜひ一度酵素風呂を体験してみて下さい。
(きばこ酵素風呂) 2025年9月22日 11:26
女性ホルモンの分泌減少が、自律神経にも影響を及ぼす
今回は「女性ホルモンの分泌減少が、自律神経にも影響を及ぼす」というテーマです。
自律神経をコントロールしているのは、脳にある視床下部。
女性ホルモン分泌の指令を出しているのと同じ場所です。
視床下部には他に感染に対抗するための免疫の機能もあり
これらを調整しながら体内の状態を一定に保っています。
しかし、更年期になると卵巣の機能が低下し、視床下部からの
「女性ホルモンを分泌しなさい」という指令に応えられなくなります。
すると、視床下部は混乱し、視床下部のコントロール下にある自律神経にまで
影響が及んでしまうのです。
更年期症状に多いホットフラッシュや汗、冷え、動悸、倦怠感などは
自律神経の乱れから引き起こされるものです。
<参考書籍>
更年期に効く美女ヂカラ(リベラル社・2023)
著者:高尾美穂
【 きばこより一言 】
酵素風呂入酵により、身体の芯から温まることで血流改善され
免疫力向上に伴い自律神経を整えることが出来ます。
そのため
酵素風呂は更年期症状に対して、非常に有効な方法の1つなのです。
(きばこ酵素風呂) 2025年9月15日 11:30
<<前のページへ|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|次のページへ>>
100件以降の記事はアーカイブからご覧いただけます。