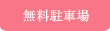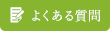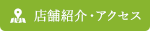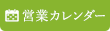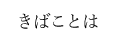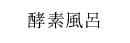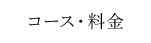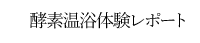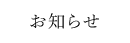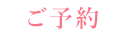カテゴリ
- もう、がんでは死なない (32)
- このクスリがボケを生む! (30)
- 口臭 (1)
- 47の心得 (77)
- アレルギー (4)
- 便 (13)
- 自律神経 (27)
- 運動 (24)
- メタボリックシンドローム (6)
- 体温 (42)
- 血液 (22)
- ストレス (41)
- 呼吸 (5)
- 酵素風呂きばこ案内 (52)
- ファスティング (6)
- 酵素風呂の記事 (10)
- 酵素栄養学 (79)
- 白湯 (8)
- 酵素とは? (11)
- 汗 (23)
- 酵素風呂 (54)
- 冷え (62)
- ダイエット (7)
- ゲルマニウム温浴 (7)
- プレ更年期1年生 (40)
- 医者が患者に教えない病気の真実 (57)
- 更年期に効く美女ヂカラ (23)
- 食品の裏側 (51)
月別 アーカイブ
- 2025年12月 (5)
- 2025年11月 (4)
- 2025年10月 (4)
- 2025年9月 (5)
- 2025年8月 (4)
- 2025年7月 (4)
- 2025年6月 (5)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (4)
- 2025年3月 (5)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (5)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (4)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (4)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (5)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (5)
- 2022年9月 (5)
- 2022年8月 (5)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (5)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (4)
- 2021年11月 (5)
- 2021年10月 (4)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (5)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (5)
- 2021年5月 (6)
- 2021年4月 (6)
- 2021年3月 (6)
- 2021年2月 (5)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (5)
- 2020年9月 (6)
- 2020年8月 (7)
- 2020年7月 (6)
- 2020年6月 (7)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (7)
- 2020年3月 (6)
- 2020年2月 (6)
- 2020年1月 (6)
- 2019年12月 (7)
- 2019年11月 (6)
- 2019年10月 (6)
- 2019年9月 (7)
- 2019年8月 (6)
- 2019年7月 (7)
- 2019年6月 (6)
- 2019年5月 (6)
- 2019年4月 (7)
- 2019年3月 (7)
- 2019年2月 (6)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (6)
- 2018年11月 (4)
- 2018年10月 (5)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (4)
- 2018年7月 (5)
- 2018年6月 (4)
- 2018年5月 (4)
- 2018年4月 (5)
- 2018年3月 (4)
- 2018年2月 (4)
- 2018年1月 (5)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (4)
- 2017年10月 (4)
- 2017年9月 (4)
- 2017年8月 (4)
- 2017年7月 (5)
- 2017年6月 (8)
- 2017年5月 (11)
- 2017年4月 (11)
- 2017年3月 (6)
- 2017年2月 (7)
- 2017年1月 (13)
- 2016年12月 (9)
- 2016年11月 (11)
- 2016年10月 (9)
- 2016年9月 (10)
- 2016年8月 (11)
- 2016年7月 (19)
- 2016年6月 (21)
- 2016年5月 (14)
- 2016年4月 (6)
- 2016年3月 (1)
最近のエントリー
ブログ 9ページ目
含硫アミノ酸摂取のポイント 〜タマネギ調理法〜
今回は「含硫アミノ酸摂取のポイント」というテーマです。
タマネギやニンニクなどに含まれる含硫アミノ酸が、男性ホルモンであるテストステロンを増やしてくれるわけですが、この含硫アミノ酸は放置すると自己分解して、どんどん失われてしまうことがわかっています。
植物の中に入っている様々な酵素が、含硫アミノ酸を分解して、壊してしまうのです。
なので、テストステロンを増やす食べ方として、タマネギの皮を剥いたら、すぐに丸ごと電子レンジにかけてしまうことです。
電子レンジで加熱すると、含硫アミノ酸を壊してしまう酵素を不活性することができます。
その後、ゆっくり切ってから料理をしていけば、含硫アミノ酸が長持ちします。
加熱することで臭いも少なくなり、テストステロンも増えます。
そして、含硫アミノ酸は抗酸化作用が強く、血小板が固まるのを抑えるので、血液がサラサラになり、動脈硬化抑制作用があると言われています。
また、放射能防護効果もあるので、現代の日本人にとっては様々な意味で有効活用すべき食品です。
さらに、タマネギは交感神経を興奮させるノルエピネフリンを出しますので、体温が上がり、脂肪細胞を燃焼させることがわかっており、ダイエットにも有効です。
<参考文献>
医者が患者に教えない病気の真実 (幻冬舎・2013)
著者:江田証
【 きばこより一言 】
食物に含まれる「酵素」は熱に弱いため、加熱調理には向いていません。
そのため、酵素を摂るためには「生」の状態の食材を摂るように心掛けましょう。
(きばこ酵素風呂) 2024年6月17日 19:13
タマネギが男性力をアップさせる?
今回は「タマネギが男性力をアップさせる?」というテーマです。
昔からタマネギやニンニク、ネギやニラなどは「精のつく」食べ物であると言われてきました。
最近の研究で、タマネギをはじめとするユリ科ネギ属の植物中の「含硫アミノ酸」にテストステロンを増やす効果があることが科学的に検証されました。
「テストステロン」とは、男性ホルモンの1つであり、筋肉質な身体や骨格、生殖機能の向上、精神面など多岐に渡り影響を及ぼす、重要な性ホルモンです。
そんなテストステロンが、ストレス社会の中で減ってきていることが問題となっています。
テストステロン不足により、苛立ち・抑うつ・睡眠低下・内臓脂肪増加・性的機能低下・意欲減退・筋力低下・骨粗鬆症など様々なことが起こります。
これを、加齢男性性腺機能低下症候群と呼びます。
これに対抗するために、中高年の男性ほどタマネギを食べて男性力をアップさせる必要があるのです。
医者が患者に教えない病気の真実
(幻冬舎・2013)著者:江田証
【 きばこより一言 】
しかしながら、良いとされる食品を摂ったとしても
体内酵素が充分な身体でなければ
その栄養を取り入れた後にその効果を発揮することはできません。
効果を発揮できる身体に必要な酵素は
酵素風呂入酵で身体から吸収でき、酵素ドリンクでは酵素その物を飲むことで
酵素をたっぷりと身体に入れる事ができます。
{関連記事はこちら}
[メタボリックシンドロームの原因について]
(きばこ酵素風呂) 2024年6月10日 12:13
喫煙とガンとメタボリック
今回は「喫煙とガンとメタボリック」というテーマです。
タバコの煙は4000種類以上の化学物質を含有しています。
その中には60種類の発ガン物質が存在します。
殺虫剤に含まれるヒ素、車のバッテリーに含まれるカドミウム、排出ガスに含まれる一酸化炭素などです。
また、喫煙者は非喫煙者と比較して、3倍以上メタボリック(内臓脂肪)症候群になりやすいのです。
喫煙しながら運動しても、運動効果が減ってしまうこともわかっています。
そして、心筋梗塞や脳梗塞など血管の病気になりやすいだけでなく、認知症になるリスクも高まります。
寿命と喫煙の関係では、喫煙を続けると寿命が10年短くなると言われています。
35歳の人が70歳まで生きている割合は、非喫煙者が81%に対し、喫煙者では58%と有意な差が見られます。
若いうちに禁煙すればするほど寿命を取り戻せるという統計もあります。
<参考文献>
医者が患者に教えない病気の真実
(幻冬舎・2013) 著者:江田証
但し、酵素風呂への定期入酵により、自身の免疫力を上げておけば
身体の機能が上がり、体内に入ってしまった有害物質排除や
維持酵素の働きにより、エネルギー回路円滑の助けが進みデトックス(毒素出し)効果をアップさせます!
{関連記事はこちら}
[タバコはメリットなし]
[メタボリックシンドロームとは?]
(きばこ酵素風呂) 2024年6月 3日 12:22
イカ・タコで胃の細胞の自殺を防げ
今回は「イカ・タコで胃の細胞の自殺を防げ」というテーマです。
胃の細胞は、生まれてある程度時間が経つと自動的に死んでいきます。
これをアポトーシス(プログラムされた細胞死:細胞自殺)と呼びます。
人間が生まれて大人になり、子孫を残すと、あとは子供に役割を任せて死んでいくのに似ています。
この胃の細胞のアポトーシスを抑え、長生きさせてくれる作用がある成分がわかってきています。
その代表が「タウリン」です。
タウリンは抗酸化ストレス作用を持っており、胃の細胞の老化や早まる自殺を予防してくれることがわかっています。
そして、タウリンを多く含むのはイカやタコ、マグロやホタテ、カキといった魚介類です。
また、タウリンを効果的に摂るコツがあります。
それはビタミンCを同時に摂ることです。
ビタミンCはタウリンの効果を長持ちさせることがわかっています。
ですから、カキにビタミンCを多く含むレモンやすだちを絞って食べるのは理にかなっているのです。
<参考文献>
医者が患者に教えない病気の真実
(幻冬舎・2013)
著者:江田証
(きばこ酵素風呂) 2024年5月27日 14:22
ブロッコリーがピロリ菌を死滅させる?
胃の調子がすぐれない人におすすめなのが、何と言ってもブロッコリーです。
ブロッコリーは、まさに胃にとっては「お薬野菜」と言っても過言ではありません。
ブロッコリーは、胃炎を抑えることがわかっているのです。
ブロッコリーには「スルフォラファン」という成分が含まれています。
スルフォラファンは胃炎の原因となるピロリ菌を抑え込んで、胃炎を改善する効果が確認されています。
また、ブロッコリーの芽(ブロッコリースプラウト)にも、このスルフォラファンがより多く含まれています。
更にピロリ菌の増殖を抑え、ピロリ菌の菌量を下げ、細胞のガン化を防ぎます。
また、胃粘膜の抗酸化作用を高め、細胞の老化を防ぎます。
そして、スルフォラファンは発ガン物質を解毒し、生体の抗酸化作用を高めることがわかっているので、ブロッコリーはガンを抑える効果が大きく期待されているのです。
cf.酵素風呂に入酵し、免役力が向上することでガンのリスクを減らすことが出来ます。
<参考文献>
医者が患者に教えない病気の真実
(幻冬舎・2013)
著者:江田証
(きばこ酵素風呂) 2024年5月20日 19:12
副交感神経を高めると胃が喜ぶ
人間は緊張すると、「交感神経」が高まります。
そして、交感神経が高まると胃腸の動きは抑えられてしまいます。
逆にリラックスすると、「副交感神経」が高まります。
副交感神経が興奮すると、胃の動きは良くなります。
胃がよく動くようになると、胃もたれや胃痛も感じにくくなるのです。
では、副交感神経を高めるにはどうしたらいいのでしょうか?
例えば、食事の時にはリラックスできる音楽を聴いてみましょう。
また、回転の早い慌ただしい店での食事ではなく、ゆっくり食べられる場所で食べると良いです。
できなければ公園などで1人でお弁当でも大丈夫です。
その際、お弁当はなるべく脂肪を抑えた内容にしてください。
他にも、自律神経を整えるためにぬるめのお風呂にゆっくり浸かったり、1日数回は深呼吸をして空を眺めてみることで、概日リズム(約24時間周期で変動する生理現象)を整えましょう。
<参考文献>
医者が患者に教えない病気の真実
(幻冬舎・2013)
著者:江田証
(きばこ酵素風呂) 2024年5月13日 13:06
ミントは胃の動きを鈍くさせる?
今回は「ミントは胃の動きを鈍くさせる?」というテーマです。
爽やかな口当たりで人気のあるミントですが、胃の動きが悪い人はミントの摂りすぎには注意が必要です。
なぜなら、実はミントには胃の動きを抑える作用があるからです。
胃内視鏡(胃カメラ)を行う際には、胃の粘膜を観察しやすくするために胃の収縮を抑える必要があります。
昔は、胃カメラを行うときには胃の動き(蠕動運動)を抑えるために注射をしていました。
これが筋肉注射のため、非常に痛くて患者さんには苦痛のタネでした。
胃カメラを受ける前には、患者さんは非常に緊張しています。
その上に腕に痛い注射をされると、苦痛も倍に感じられるのです。
現在は、ミントで作った薬液が開発されており、胃カメラを行うときに胃の中にこのミント液を撒くのです。
そうすると、このミントが胃の動きをあっという間に抑えて、観察が非常に楽になります。
ミントの働きも使い方次第なのです。
胃がもたれたり、張ったりする症状は胃の動きが悪いサインです。
胃の動きのリズムを正常にするためには、胃の動きを弱めるものは避ける必要があります。
そうした点で、ミントの摂りすぎには注意が必要なのです。
<参考文献>
医者が患者に教えない病気の真実
(幻冬舎・2013)
著者:江田証
(きばこ酵素風呂) 2024年5月 6日 20:13
機能性胃腸症の症状を軽くする方法 ~④ピロリ菌による影響~
今回は機能性胃腸症の症状を軽くする方法
「④ピロリ菌による影響」というテーマです。
ピロリ菌に感染していると、ほぼ間違いなく胃炎が起こります。
このピロリ菌を除菌すると、胃の症状が改善する人も多いので、感染が判明した人はまず除菌を試してみる価値があります。
ピロリ菌感染があると動脈硬化を起こしたり、ビタミンCが体内で十分に役割を発揮できなかったり、認知症の率が高まったりと、全身に悪影響を及ぼします。
そのため、早い年齢での除菌が望ましいところです。
胃ガンを抑えるには、40歳未満で除菌すると1番効果が出やすいということがわかっています。
<参考文献>
医者が患者に教えない病気の真実
(幻冬舎・2013)
著者:江田証
(きばこ酵素風呂) 2024年4月29日 20:13
機能性胃腸症の症状を軽くする方法 ~③遅延型フードアレルギー 胃の不調はアレルギーの可能性がある~
「③遅延型フードアレルギー 胃の不調はアレルギーの可能性がある」というテーマです。
通常、アレルギーというと食べて数秒から数分で起こる「呼吸困難」「発疹」「ショック」などを指します。
これを即座型アレルギーと呼びます。
それに対し、「遅延型フードアレルギー」というものがあります。
これは、食べて数時間から24時間後に腹痛や下痢、頭痛や全身の怠さなどが生じるもので、遅れて症状が出るため、本人が食事との関連に気づかないといった落とし穴があります。
通常の即時型アレルギーはIgE抗体というものを介して起こるのですが、遅延型フードアレルギーはIgG抗体を介したアレルギー反応です。
少量の血液を採るだけで検査可能であり、これにより胃痛の原因がわかり、そのような食事の抗原を避けることで、驚くほど腹痛が減った患者さんは多いのです。
また、どんな食べ物を食べた後、何時間くらい経ってから調子が悪くなったか、メモしておくと食べ物のアレルギーの推測がつくことがあります。
<参考文献>
医者が患者に教えない病気の真実
(幻冬舎・2013)
著者:江田証
(きばこ酵素風呂) 2024年4月22日 11:23
機能性胃腸症の症状を軽くする方法 ~②胃の知覚過敏~
今回は機能性胃腸症の症状を軽くする方法
「②胃の知覚過敏」というテーマです。
胃の調子がすぐれない人、特に胃の「痛み」として感じる人の特徴は、胃の感覚が敏感すぎる人です。
感覚閾値(刺激がある値以上に強くなければ反応は起こらない、その限界値のこと)が低下しているとも言います。
胃の中にバルーンという風船を入れて、膨らませながらfMRI(ファンクショナルMRI)を用いて、内臓の知覚過敏を脳の血流増加として調べた研究があります。
すると、わずかしか風船を膨らませていないにも関わらず、健康な胃の人と比べて、「脳の側頭葉の痛みを感じる部分」と「左右の脳の前下回という部分」がすぐに活性化されました。
胃の刺激に対して、「脳が感じやすい」状態になっていることがわかります。
これは胃の知覚過敏と脳が深い関係にあることを示しています。
<参考文献>
医者が患者に教えない病気の真実
(幻冬舎・2013)
著者:江田証
(きばこ酵素風呂) 2024年4月15日 12:53
<<前のページへ|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|次のページへ>>
100件以降の記事はアーカイブからご覧いただけます。