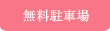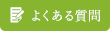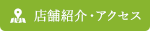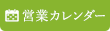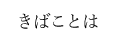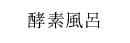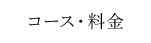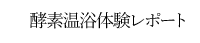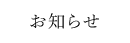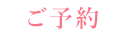カテゴリ
- もう、がんでは死なない (32)
- このクスリがボケを生む! (30)
- 口臭 (1)
- 47の心得 (77)
- アレルギー (4)
- 便 (13)
- 自律神経 (27)
- 運動 (24)
- メタボリックシンドローム (6)
- 体温 (42)
- 血液 (22)
- ストレス (41)
- 呼吸 (5)
- 酵素風呂きばこ案内 (51)
- ファスティング (6)
- 酵素風呂の記事 (10)
- 酵素栄養学 (79)
- 白湯 (8)
- 酵素とは? (11)
- 汗 (23)
- 酵素風呂 (54)
- 冷え (62)
- ダイエット (7)
- ゲルマニウム温浴 (7)
- プレ更年期1年生 (40)
- 医者が患者に教えない病気の真実 (57)
- 更年期に効く美女ヂカラ (21)
- 食品の裏側 (51)
月別 アーカイブ
- 2025年12月 (2)
- 2025年11月 (4)
- 2025年10月 (4)
- 2025年9月 (5)
- 2025年8月 (4)
- 2025年7月 (4)
- 2025年6月 (5)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (4)
- 2025年3月 (5)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (5)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (4)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (4)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (5)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (5)
- 2022年9月 (5)
- 2022年8月 (5)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (5)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (4)
- 2021年11月 (5)
- 2021年10月 (4)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (5)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (5)
- 2021年5月 (6)
- 2021年4月 (6)
- 2021年3月 (6)
- 2021年2月 (5)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (5)
- 2020年9月 (6)
- 2020年8月 (7)
- 2020年7月 (6)
- 2020年6月 (7)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (7)
- 2020年3月 (6)
- 2020年2月 (6)
- 2020年1月 (6)
- 2019年12月 (7)
- 2019年11月 (6)
- 2019年10月 (6)
- 2019年9月 (7)
- 2019年8月 (6)
- 2019年7月 (7)
- 2019年6月 (6)
- 2019年5月 (6)
- 2019年4月 (7)
- 2019年3月 (7)
- 2019年2月 (6)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (6)
- 2018年11月 (4)
- 2018年10月 (5)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (4)
- 2018年7月 (5)
- 2018年6月 (4)
- 2018年5月 (4)
- 2018年4月 (5)
- 2018年3月 (4)
- 2018年2月 (4)
- 2018年1月 (5)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (4)
- 2017年10月 (4)
- 2017年9月 (4)
- 2017年8月 (4)
- 2017年7月 (5)
- 2017年6月 (8)
- 2017年5月 (11)
- 2017年4月 (11)
- 2017年3月 (6)
- 2017年2月 (7)
- 2017年1月 (13)
- 2016年12月 (9)
- 2016年11月 (11)
- 2016年10月 (9)
- 2016年9月 (10)
- 2016年8月 (11)
- 2016年7月 (19)
- 2016年6月 (21)
- 2016年5月 (14)
- 2016年4月 (6)
- 2016年3月 (1)
最近のエントリー
ブログ 4ページ目
動悸に対するケア
今回は「動悸に対するケア」というテーマです。
激しく動いたわけではないのに、突然バクバクするのはいわゆる「動悸」
という状態かもしれません。
女性ホルモンの減少によって自律神経が乱れて、動悸や息切れなどが起きることが
あります。
[ケア]
①漢方:体力があるタイプには「柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)」が効果的です。
一方、不安感が強く、体力に自信がないタイプには「加味逍遙散(かみしょうようさん)」がおすすめです。
また、「半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)」も動悸症状に効果があります。
②休養:更年期は親の介護や死、子供の進学や就職など、今まで経験したことのない
ストレスに直面する時期と重なります。
こういった心理的ストレスも動悸を誘発しますので、日頃からうまく
ストレスを発散させましょう。
動悸を感じたら、全てのことを中断して症状が落ち着くまで安静にします。
③生活改善:血圧を上昇させるアルコール、カフェイン、タバコは、動悸息切れを誘発する可能性があります。
これらは極力控え、出来れば禁煙をおすすめします。
また、睡眠不足も動悸を引き起こす原因になります。
規則正しい生活を心掛けて、睡眠の質を高めるようにしてください。
<参考書籍>
プレ更年期1年生(つちや書店・2019)
著者:対馬ルリ子
【 きばこより一言 】
そして、酵素風呂で身体の芯を温めて血流改善をする事で
体調を整えてあげるのも一つのケア方法です。
酵素風呂入酵では、代謝が上がり免疫力が高まりますので
必要な自然治癒力により、動悸の原因の改善が期待できます。
(きばこ酵素風呂) 2025年5月12日 18:50
肩こりに対するケア
今回は「肩こりに対するケア」というテーマです。
血行が悪くなって、疲労物質である乳酸が筋肉の中に留まり
かたまってしまうのが肩こりの正体です。
血流をよくする生活を心掛け、血行が悪くなりがちなプレ更年期を乗り切りましょう。
①運動:同じ姿勢を続けていると、肩こりがひどくなります。
特にパソコンモニターを見続けるデスクワークは目を酷使するため、疲れが溜まりがち。
仕事中でも1時間に1回は肩や首を回したり、両腕を上に伸ばしてストレッチをしましょう。
また、普段から猫背にならないように注意することも大切です。
②入浴:バスタイムは筋肉のコリをほぐす絶好の時間です。
入浴でじっくりと身体を温めることで、血行が良くなり、肩こりも緩和されます。
暑い夏でも、実は冷房で身体が冷えている可能性があります。
シャワーだけで済ませず、1年を通して湯船に浸かって血行を促進し
肩こりを予防しましょう。
③ツボ:手の甲の親指と人差し指の間の付け根にある「合谷」は
肩こりや頭痛、目の疲れに効く万能のツボとして有名です。
痛気持ちいいぐらいの力加減で2〜3秒ほど、じんわり指圧しましょう。
<参考書籍>
プレ更年期1年生(つちや書店・2019)
著者:対馬ルリ子
【 きばこより一言 】
入浴でじっくりと身体を温めることも良いのですが
「酵素風呂」では更に身体を芯からじっくりと温めることができるので
肩こりのケアにはもってこいの方法です。
また、きばこのオプショナルメニューである
「癒しのアイマスク」は、テレビやパソコン・スマホなどで酷使した目の
血流を改善するのでこちらもおすすめです。
(きばこ酵素風呂) 2025年5月 5日 11:42
睡眠に対するケア
よく眠れない、寝つきが悪い、眠りが浅い、朝早く目が覚めてしまうなどの睡眠に対する悩みは
プレ更年期によくある症状です。
そんな睡眠への対策を挙げていきます。
①生活改善:朝起きたら、カーテンを開けて太陽の光を浴びましょう。
もしできれば、30分ほどウォーキングをして目を覚ますとなお良いでしょう。
長時間の昼寝、カフェインやタバコ、アルコールは睡眠の質を悪くするので控えましょう。
また、就寝1時間前にはテレビやスマホもオフにし、ゆったりと過ごすようにしてください。
②呼吸:仰向けになって、軽く目をつぶります。
スーッと口から息を吐き、吐ききったら1〜2秒息を止めます。
今度は鼻から息を吸い込み、吸いきったら1〜2秒止めます。
これを3〜4回繰り返します。
呼吸に集中することで「副交感神経」が優位になり、眠りやすくなります。
③ハーブ:質の良い睡眠には、カフェインはできるだけ避けたいところです。
そこでおすすめは、ノンカフェインのハーブティー。
特におすすめはカモミール、ラベンダー、ローズです。
香りとともにくつろぐ時間が、疲れた身体と心を癒し、安眠へと誘います。
<参考書籍>
プレ更年期1年生(つちや書店・2019)
著者:対馬ルリ子
【 きばこより一言 】
そして酵素風呂は、「睡眠に対するケア」としても
上記に掲げた対策のひとつに加えたいツールとなります。
酵素風呂に定期的に入酵する事で
更年期の症状全般に対する改善効果もあります。
実際、きばこ酵素風呂『体験者の声』には
寝付きが良くなった!
身体が温まってぐっすり眠れた!
不眠症が治まった! 睡眠薬の常用がなくなった!
等の声が多く寄せられており、リンクを貼りましたので
こちらを読んで参考にしてみて下さい。
(きばこ酵素風呂) 2025年4月28日 12:35
月経前症候群(PMS)に対するケア
今回は「月経前症候群(PMS)に対するケア」というテーマです。
月経前に精神的に不安定になるPMSは、女性ホルモンの変動が原因です。
女性ホルモンが減り始めるとイライラしやすくなり、プレ更年期はその症状が現れやすいです。
そんな月経前症候群(PMS)への対策を挙げていきます。
①アロマテラピー:香りは心を穏やかにする効果があります。
イライラしたら、アロマテラピーを取り入れてみましょう。
心を鎮めたいならラベンダーやカモミール、気持ちをスッキリさせたいなら
レモンやオレンジなどの柑橘系がおすすめです。
枕やハンカチに1〜2滴落とすだけでも効果があります。
②運動:運動を習慣化すると自律神経が整い、気持ちをコントロールしやすくなります。
ストレスを感じるほどの運動はよくありませんが、「心地良く汗をかく程度の運動」
を日頃から取り入れてみてください。
ヨガやピラティスの他、ゴルフやテニスなどを習ってみるのもおすすめです。
③睡眠:睡眠不足が続くと、誰でもイライラが抑えられなくなります。
まずは、たっぷりと睡眠時間を確保してください。
うまく眠れないときは、マッサージや半身浴でリラックスを心掛けましょう。
<参考書籍>
プレ更年期1年生(つちや書店・2019)
著者:対馬ルリ子
【 きばこより一言 】
酵素風呂への入酵でも
上記①②③対策の効果を充分に得る事ができます。
生理中の入酵ならば、最適ですね!
尚、酵素風呂きばこでは生理の時でも入酵が可能です。
その時には下着とナプキンの替えを2セット
ビニールに入れてご持参ください。
(きばこ酵素風呂) 2025年4月21日 10:35
耳鳴りに対するケア
耳鳴りは、耳の内部の「内耳」が興奮して、本来は鳴っていないはずの音の信号を
脳に送ってしまうのが原因と考えられています。
そんな耳鳴りへの対策を挙げていきましょう。
①運動:軽い運動を心掛けることで、血流が促進され、自律神経が整ってきます。
まずは1日10分程度の軽いウォーキングから始めてみましょう。
ただし、耳鳴りに眩暈の症状が伴う場合は安静が第一なので、運動は控えましょう。
②睡眠:脳の疲れが耳鳴りに関係していることが指摘されています。
過剰なストレスからよく眠れなくなると、症状が出やすくなるようです。
意識的にストレスを発散するとともに、アロマの香りを取り入れて質のよい眠りを
確保しましょう。
また、適度な運動習慣も眠りにはとても大切です。
③嗜好品:喫煙習慣やカフェインの過剰摂取は耳鳴りの危険因子です。
禁煙し、カフェインも控えましょう。
また、アルコールも眠りの質を下げるので、寝酒はおすすめできません。
辞めることがストレスなら、お酒は1日おき、タバコの本数は減らすなど
出来ることから始めてください。
<参考書籍>
プレ更年期1年生(つちや書店・2019)
著者:対馬ルリ子
【 きばこより一言 】
酵素風呂では、身体の芯が温められるので
血流の改善が大きく
酵素室での癒し効果も高いためストレス改善と
良い睡眠を導きます!
そして、短時間で大量の汗もかく為
20分間の入酵で、エアロビクス2時間分の効果になります。
また、定期的に入酵すれば
嗜好品による害の軽減にも繋がります。
(きばこ酵素風呂) 2025年4月14日 20:17
眩暈(めまい)に対するケア
眩暈には、自分や周囲がぐるぐる回る「回転性眩暈」と、身体がフワフワする「浮動性眩暈」があり、回転性眩暈は耳鳴りや立ちくらみ、頭痛を併発する場合もあります。
そんな眩暈に対する対策を挙げていきましょう。
①安静:眩暈の症状が出ているときに無理して動くと、転倒してしまう危険性があります
すぐにその場に座る、壁に寄りかかる、横になれる馬車があれば横になるなどして、しばらく安静にしてください。
少し楽になってきたら深呼吸をして、気持ちを落ち着けてからゆっくり動きます。
②休養:眩暈にはストレスが大きく関係していると言われています
ストレスを解消するには、意識的に身体と心をしっかり休めることが大切です。
③食事:食生活が乱れると、血流はますます悪くなり、眩暈が起きやすくなります
まずは、規則正しい野菜中心の食生活を心掛けましょう。
血流を良くするビタミンEが豊富なカボチャやブロッコリーのほか、疲労回復効果のあるビタミンB群が含まれるウナギやレバーは積極的に摂りたい食材です。
<参考書籍>
プレ更年期1年生(つちや書店・2019)
著者:対馬ルリ子
【 きばこより一言 】
体質改善のできる酵素風呂入酵で
ストレスで落ちてしまっている代謝を上げ
自然治癒力(免疫力)効果を上げる事や
全身から酵素を吸収できる酵素風呂なら
乱れた食生活で具合の悪くなってしまった身体の
改善も望めます!
また、酵素の力には疲労回復効果も期待できます。
(きばこ酵素風呂) 2025年4月 7日 18:08
むくみに対するケア
今回は「むくみに対するケア」というテーマです。
むくみは運動不足や睡眠不足、塩分の摂り過ぎなどが原因ですが
筋力が低下するプレ更年期では下半身から心臓へのぼる血流が弱くなることが
影響しています。
そんな、むくみの対策はどのようなことをすればよいのでしょうか?
①運動: むくみ解消には、運動がおすすめです。
積極的に階段を使ったり、隣駅まで歩いてみるなど、自身に無理のない範囲で身体を動かす習慣を作りましょう。
また、筋肉量を増やすと血液循環が良くなり、老廃物の排出がスムーズになります。
家事の合間に軽いスクワットなどの筋トレを取り入れるなどしてみてください。
②マッサージ: 足がむくんでだるいときなどは、運動とセットといってもいいぐらいの対策である
マッサージを行ってみてください。
その際は足の裏を揉んでよくほぐしてから、足首→ふくらはぎ→膝裏の順にマッサージしていきます。
これは、滞った血流を下から上へと流してあげることが目的なので
足裏から膝に向かって揉みほぐすのがポイントです。
③食事: むくみが気になるからといって水分を控えることはNGです。
体内の循環を良くすることが大切なので、水分をしっかり摂って、しっかり排出することを心掛けます。
また、塩分の摂り過ぎにも注意しましょう。<参考書籍>
プレ更年期1年生(つちや書店・2019)
著者:対馬ルリ子
【 きばこより一言 】
むくみの解消に
酵素風呂きばこでは、集中デトックスコースがあります。
【酵素温浴】 + 【ゲルマ温浴】 + 【マッサージチェアー】 約120分 ※要予約
デトックス(毒素出し)効果に優れています!
冷え・むくみの酷い方、風邪の症状があり具合の悪い時・調子のすぐれない時等に
スッキリ改善できます!
【マッサージチェアー】は他のオプショナルメニューに変更することもできます
●きばこ体験者の声『むくみ』の解消 ⇒詳細はコチラ
●ゲルマ温浴とは ⇒詳細はコチラ
●ゲルマニウムとゲルマ温浴の利点 ⇒詳細はコチラ
(きばこ酵素風呂) 2025年3月31日 15:17
ホットフラッシュへの対策
今回は「ホットフラッシュへの対策」というテーマです。
とにかく暑いと感じたり、汗が止まらないといった症状は「ホットフラッシュ」と呼ばれており
更年期に多く見られます。
これらの症状は自律神経の乱れによるもので、体温や汗のコントロールがうまく出来なくなっている状態です。
そんなホットフラッシュにはどのような対策を取ればよいのでしょうか?
【対策】
①運動 :適度な運動習慣が、乱れた自律神経を整えてくれます。
身体を動かすことで血行が良くなり、健康的な汗がかけるようになります。
出来れば、ちょっと汗ばむ程度のウォーキングがおすすめで、気持ちよく汗をかくことで気分爽快です。
運動後はゆっくりお風呂に入ってリラックスしましょう。
②食事:のぼせ=冷たいものでクールダウンを、と思っていませんか?
残念ながら、冷たいものでは余計に自律神経を乱してしまいます。
暑い夏でも常温以上の飲み物にしましょう。
菊はのぼせによく効く食材なので、おひたしや酢の物にして、食生活に取り入れてみてください。
③衣類:ホットフラッシュで悩む人の中には、意外にも冷え性の人が多くいます。
いわゆる「冷えのぼせ」という状態です。
涼しくするだけではなく、冷やさない工夫も心掛けましょう。
ストールなどの羽織るもの、レッグウォーマーや手袋などで身体を冷やさない工夫をしてください。
<参考書籍>プレ更年期1年生(つちや書店・2019)
著者:対馬ルリ子
【 きばこより一言 】
また、ホットフラッシュの症状は
酵素風呂の定期入酵で、悪い汗から良い汗をかけるようになると
ほとんど治まります。
酵素風呂では、多量の汗をかくことができ
入酵後の汗腺トレーニング(自分でかく汗で体温を下げる)
で良い汗に改善させます。
良い汗とは、汗の匂いやベタベタしない
限りなく水に近い汗で
体温が上がった時に、体温を下げる働きの大きい汗の事です。
良い汗がかける様になると
ホットフラッシュに限らず、猛暑の夏も過ごしやすくなります。
(きばこ酵素風呂) 2025年3月24日 14:27
漢方医学による『気・血・水』の考え方
漢方は、中国から5〜6世紀頃に伝わり、日本で独自に発展した医学です。
漢方では、人間の身体は「気・血・水」の3つで構成されると考えます。
①「気」は体内に流れるエネルギーのことで身体を機能させて代謝を促すもの。
②「血」は血液そのもので全身の組織と器官に栄養を送る役割をするもの。
③「水」はリンパ液や尿、肌の潤いなど血液以外の水分のことです。
この3つのバランスが保たれた状態が「健康」であり、少なくても多くても
身体のバランスは崩れてしまいます。
●「気」の特徴
不足→「気虚」
疲れやすく、無気力な状態に。免疫力の低下から風邪をひきやすくなる。
過多→「気滞」
気分がすぐれず、抑うつ感、イライラ、不眠など精神神経症状が現れやすくなる。
●「血」の特徴
不足→「血虚」
栄養不良状態になり、貧血や皮膚乾燥などが見られる。
顔色は青白い状態になる。
過多→「血滞」
血行が悪くなり、月経異常や肌荒れ、全身の冷えなどが現れやすくなる。
●「水」の特徴
不足→「陰虚」
身体に潤いがなく、皮膚乾燥や冷え、のぼせや便秘などが見られる。
過多→「水毒」
水分代謝が悪くなり、むくみや眩暈、胃腸障害などが現れやすくなる。
<参考書籍>
プレ更年期1年生(つちや書店・2019)
著者:対馬ルリ子
【 きばこより一言 】
まさしく、酵素風呂の自然発酵熱での温浴は
この漢方医学の考え方に則した温浴法になります。
人間の身体の「気・血・水」の3つを効果的に改善させ
さらに生きていく為に必須の酵素も全身から吸収できるのです。
身体のバランスが保たれた健康維持の為に
酵素風呂が、最適なツールとなるでしょう。
(きばこ酵素風呂) 2025年3月17日 13:22
メンタル不調の整え方
リフレッシュ法として、2つ紹介します。
●マインドフルネス
マインドフルネスとは、「今、ここ」に集中する心のあり方のこと。
どんな大勢でもよいので、雑念を持たず、心をリラックスさせ、呼吸だけに集中することがポイントです。
毎日行い習慣化することで、気持ちの切り替えができるようになり、集中力の向上、イライラの解消
睡眠障害の改善などの効果が期待でき、更年期症状の緩和にも役立ちます。
●カウンセリング
「友達に悩みを話してスッキリした」という経験は、誰にでもあるかと思います。
プレ更年期は気分が落ち込み、何事も深刻に考えがちです。
気軽に相談できる友人や家族に話を聞いてもらうだけでも、気持ちが楽になります。
更年期で悩んでいる人たちの集いやセミナーに参加するのもおすすめですし
専門家を頼るのも1つの手段です。
<参考書籍>
プレ更年期1年生(つちや書店・2019)
著者:対馬ルリ子
【 きばこより一言 】
そして、酵素風呂もメンタル不調を整えるには
最適なリフレッシュ法方と言えます!
酵素温浴中の室内には、森林と同様の
発酵の際に発生するマイナスイオンやフィトンチッド
ヒノキのほのかな香りで心をリラックスさせ気分を落ち着かせる物質で
満ち溢れています!
ふわふわのキノキパウダーの中に身体をゆだね
呼吸だけに集中した20分間を過ごす事で
メンタルのみならず、発酵熱で身体を芯から温めるので
全身の血流改善による細胞の活性化と酵素吸収ができます。
(きばこ酵素風呂) 2025年3月10日 09:15
<<前のページへ|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|次のページへ>>
100件以降の記事はアーカイブからご覧いただけます。