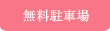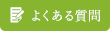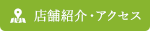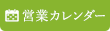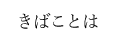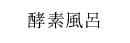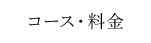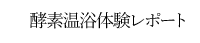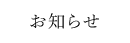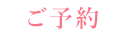カテゴリ
- もう、がんでは死なない (32)
- このクスリがボケを生む! (30)
- 口臭 (1)
- 47の心得 (77)
- アレルギー (4)
- 便 (13)
- 自律神経 (27)
- 運動 (24)
- メタボリックシンドローム (6)
- 体温 (42)
- 血液 (22)
- ストレス (41)
- 呼吸 (5)
- 酵素風呂きばこ案内 (51)
- ファスティング (6)
- 酵素風呂の記事 (10)
- 酵素栄養学 (79)
- 白湯 (8)
- 酵素とは? (11)
- 汗 (23)
- 酵素風呂 (54)
- 冷え (62)
- ダイエット (7)
- ゲルマニウム温浴 (7)
- プレ更年期1年生 (40)
- 医者が患者に教えない病気の真実 (57)
- 更年期に効く美女ヂカラ (22)
- 食品の裏側 (51)
月別 アーカイブ
- 2025年12月 (3)
- 2025年11月 (4)
- 2025年10月 (4)
- 2025年9月 (5)
- 2025年8月 (4)
- 2025年7月 (4)
- 2025年6月 (5)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (4)
- 2025年3月 (5)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (5)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (4)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (4)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (5)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (5)
- 2022年9月 (5)
- 2022年8月 (5)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (5)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (4)
- 2021年11月 (5)
- 2021年10月 (4)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (5)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (5)
- 2021年5月 (6)
- 2021年4月 (6)
- 2021年3月 (6)
- 2021年2月 (5)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (5)
- 2020年9月 (6)
- 2020年8月 (7)
- 2020年7月 (6)
- 2020年6月 (7)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (7)
- 2020年3月 (6)
- 2020年2月 (6)
- 2020年1月 (6)
- 2019年12月 (7)
- 2019年11月 (6)
- 2019年10月 (6)
- 2019年9月 (7)
- 2019年8月 (6)
- 2019年7月 (7)
- 2019年6月 (6)
- 2019年5月 (6)
- 2019年4月 (7)
- 2019年3月 (7)
- 2019年2月 (6)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (6)
- 2018年11月 (4)
- 2018年10月 (5)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (4)
- 2018年7月 (5)
- 2018年6月 (4)
- 2018年5月 (4)
- 2018年4月 (5)
- 2018年3月 (4)
- 2018年2月 (4)
- 2018年1月 (5)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (4)
- 2017年10月 (4)
- 2017年9月 (4)
- 2017年8月 (4)
- 2017年7月 (5)
- 2017年6月 (8)
- 2017年5月 (11)
- 2017年4月 (11)
- 2017年3月 (6)
- 2017年2月 (7)
- 2017年1月 (13)
- 2016年12月 (9)
- 2016年11月 (11)
- 2016年10月 (9)
- 2016年9月 (10)
- 2016年8月 (11)
- 2016年7月 (19)
- 2016年6月 (21)
- 2016年5月 (14)
- 2016年4月 (6)
- 2016年3月 (1)
最近のエントリー
ブログ 10ページ目
誤診が多い、胃とみぞおちの痛み
今回は「誤診が多い、胃とみぞおちの痛み」というテーマです。
「みぞおちの痛み」には注意が必要です。
まずは、みぞおちにある内臓の位置関係を説明していきます。
みぞおちの皮膚の下には、まず肝臓があります。
その裏(背中側)には、胃と十二指腸があり、その奥に膵臓が位置しています。
また、肝臓に近い胆嚢と胆管の痛みは、みぞおちに放散(響く)します。
こうした特徴から、他の医療機関から転院してくる患者さんの中には、次のようなケースが見られることがあります。
①カメラで異常はないと言われたが、みぞおちの痛みが強く来院。
腹部エコーで、胃の裏の膵臓に進行性膵臓ガンが見つかった。
②処方された胃薬を飲んでいても、症状が改善せず来院。
腹部エコーで確認すると胆石が胆嚢にあり、胆嚢炎を起こしていた。
胆嚢炎の痛みはみぞおちに響くため、患者は「胃が痛い」と誤解し、医師もそれに気づかなかった。
③胃潰瘍ではないかと診断されたが、薬を飲んでもみぞおちの痛みが改善せず来院。
腹部エコーを行うと、肝臓に直径8センチの肝臓ガンが見つかった。
胃の前には肝臓が位置しており、肝臓の腫瘍によってみぞおちが痛むことがあるので注意が必要。
このように、みぞおちの痛みには危険な誤診が多いのです。
「みぞおち=胃」という思い込みを捨てることが肝要です。
なぜなら、みぞおちの痛みは100%胃の痛みとは限らないからです。
みぞおちの痛みは、「胃」の痛みとして本人には認識されます。
しかし、胃の周りにはいくつかの臓器が入り組んで重なり合っていることを忘れてはいけません。
胃カメラによる検査で異常がないのに改善しない人、胃薬を服用しても軽快しない人は、胃以外の病気を疑って、腹部エコー検査を希望してほしいのです。
さらに万全を尽くすなら、エコーよりも死角の少ない、CT(コンピューター断層撮影装置)やMRI(磁気共鳴画像装置)検査で胃の周辺臓器の精密検査を受けることです。
<参考文献>
医者が患者に教えない病気の真実
(幻冬舎・2013)
著者:江田証
(きばこ酵素風呂) 2024年3月25日 18:00
聴診器で診断できる身体の声
聴診器はレントゲンのように被曝の心配もなく、非常に多くの身体の情報が得られます。
また、医療従事者だけでなく、誰にでも簡単に使うことができるところも便利です。
そんな聴診器で「身体の声」を聞いてみましょう。
聴診器を当ててチェックしたい部位は、①首②胸の上部(肺)③左胸(心臓)④腹部の4つです。
<こんな音が聴こえたら要注意>
①首の両側の血管に聴診器を当てます。
血管が細くなって詰まりかけているときには、「シュー、シュー」という音がします。
そんな音がしないか確認します。
首の血管(内頸動脈)が動脈硬化で詰まり、脳梗塞を起こす人が増えているのです。
聴診器によるチェックで狭窄が早期に発見できれば、血管内膜剥離術という手術で脳梗塞を防ぐことができます。
②両胸の乳首の少し上に聴診器を当てて、大きく呼吸をして、肺の音を聴いてみます。
例えば、喘息発作では息を吸ったときには「ヒューヒュー」という高い音、息を吐き終わるときには「ブーブー」という独特の低い音が聴こえます。
この時、普段から肺の音を聴いておけば、咳が出たときにただの風邪なのか、喘息発作なのかが大まかにわかるようになります。
また、心不全を起こしている人は肺水腫と言って、肺が水浸しの状態になっており、呼吸をした時に水が「ボコボコ」という音がします。
他にも、肺気腫になると肺が膨張するため、肺の音が遠くに感じるなど、聴こえづらくなります。
③心臓の音は左の乳首付近に聴診器を当てて聴き、リズムを覚えておきます。
鼓動のリズムが不規則な人の中には、心房細動の人がいます。
聴診器でチェックしたとき、鼓動のリズムが乱れると、心臓内で血液の流れが淀んで、血栓ができやすいのです。
それが脳に飛び、血管を詰まらせてしまうことで、脳梗塞になる危険性があります。
④腹部はヘソの辺りに聴診器を当てて、10秒以上聴きます。
普段から腸の音に親しんでいると、腸が詰まったり、捻れたりする腸閉塞のときに聞こえる金属性雑音(遠くでキン、キンと金属の管を叩いたような音)などの異変に気付くことができます。
何より、聴診器で身体の声を聴いていると、自分との対話ができて、心が落ち着くようになるでしょう。
<参考文献>
医者が患者に教えない病気の真実
(幻冬舎・2013)
著者:江田証
(きばこ酵素風呂) 2024年3月18日 11:12
胃の不調には3つの原因がある
今回は「胃の不調には3つの原因がある」というテーマです。
胃の不調は、生活の質や仕事の能率、幸福感などを大きく落としてしまいます。
そうならないために、「胃力」を高めることで胃を健康にすることが大切です。
胃の不調の原因は次の3つです。
①胃酸力
②胃運動力
③抗ストレス力
ひとつずつ説明していきましょう。
①胃酸力
胃酸が出過ぎている人は、胃カメラで腫瘍もなく、ガンもないのにも関わらず、胃が痛いと感じるのです。
これを、胃の「知覚過敏」と呼びます。
例えば、胃潰瘍や十二指腸潰瘍もなく、ガンもないのに胃が痛むことはよくある話なのです。
胃酸が出過ぎていると、潰瘍がないのに胃は痛むのです。
ですから、逆に胃カメラの結果が全てではない、ということが大切です。
もちろん、ガンがないか腫瘍がないか、胃カメラで調べることは極めて重要です。
しかし、胃カメラで何もないからと言って、何もしなくてもいいということではないのです。
症状が大切です。
痛みを感じる患者さんには、胃酸を抑える努力をしてもらうことで、痛みも楽になり、患者さんも救われるのです。
②胃運動力
胃の動きの鈍い人が感じる症状は、胃のもたれ、胃の重い感じ、吐き気などです。
これを胃の「運動不全」と呼びます。
胃カメラで異常がなくても、もたれ、何か重苦しい感じなどを感じたら、胃の動きを改善する工夫(脂肪を控え、運動して自律神経を整える)をすると、すっきりした気持ちで生活を送ることができます。
③抗ストレス力
胃酸を抑え、胃の動きを高め、それでも改善されないとき、考えなくてはならないのは、知らない間にかかってきているストレスや過労です。
ピロリ菌がある人にストレスがかかると、簡単に腫瘍ができてしまいます。
逆にピロリ菌がいなければ、少々のストレスがかかっても腫瘍はできないことがわかっていますので、その点では安心できます。
ストレスを感じる前に積極的にストレスを解消し、常に溜め込まないような工夫をしましょう。
ただ、過大なストレスで腫瘍になることも、ままありますので注意しなくてはなりません。
<参考文献>
医者が患者に教えない病気の真実
(幻冬舎・2013)
著者:江田証
(きばこ酵素風呂) 2024年3月11日 12:27
胃の2種類の動きを使い分ける
胃の動きには大きく分けて、「食後の運動」と「空腹時の運動」があります。
<食後の運動>
胃に食べ物が入ると、胃の出口付近の「幽門前庭部」が1分間に3回、規則的に動いて食べ物を細かく砕き、2mm以下になったものを胃から排出する。
この運動は食後3〜4時間続く。
<空腹時の運動>
午前0時から朝方までの空腹時、胃の上部の「穹窿(きゅうりゅう)部」が強く収縮して、食べ物の残りカスや脱落した胃の細胞を、一気に胃の外に押し流して掃除をする。
私たちは日中に活動し、夜中に睡眠をとっていますが、胃はこの逆で夜中の空腹時の方が、食後よりずっと活発に動いているというわけです。
しかし、夜遅くに食事をすると食後の胃の運動が夜中にも続いてしまい、空腹時の運動になかなか移行できなくなります。
胃の掃除が十分にできていないと、胃もたれに繋がり、他の臓器に回るべき血流が胃に集中するため、身体全体に負担がかかってくるのです。
夜食事をするなら、遅くとも9時までには済ませて、胃の掃除力を味方につけたいところです。
夜中にずっと動いていた胃も、明け方になると動きが鈍ります。
そして、朝になると交感神経が緊張し、胃の動きを抑制します。
また、ストレスホルモンであるCRF(Corticohormone Releasing Factor)が脳の視床下部から分泌され、胃の蠕動運動(腸管の口側が収縮し、肛門側が弛緩して内容物を先へ押し出していく運動)を弱めてしまいます。
従って、朝には胃の働きをあまり必要とせず、できれば白湯のみが望ましいと言えます。
何か食べるのであれば、酵素が含まれる生野菜や果物などを摂ると良いでしょう。
<参考文献>
医者が患者に教えない病気の真実
(幻冬舎・2013)
著者:江田証
(きばこ酵素風呂) 2024年3月 4日 18:18
舌マッサージであなたの身体はよみがえる?
今回は「舌マッサージであなたの身体はよみがえる?」というテーマです。
口や舌を活性化することが、脳の老化防止に重要なこととわかってきました。
なぜなら、口や舌に関係した脳の感覚細胞の量が非常に多いため、刺激することで脳も活性化するからです。
舌のアンチエイジングの話はあまり聞いたことがないかも知れませんが、舌をはじめとする口の中を若々しく保つことは長寿に重要なことがわかってきました。
実は歳をとってくると、舌の筋肉が薄くなってくるのです。
以前お話しした、胃がピロリ菌感染による病的老化で薄くなるのと同様に、舌にも老化が起こることで薄くなるのです。
また、手足の筋肉が加齢とともに弱くなる(サルコペニア)のと同様に、舌の筋肉もサルコペニアを起こすのです。
介護を必要としない自立している人の舌は厚いことがわかっています。
●この舌が薄くなることが、なぜ寿命を短くするのか?
日本人の死因の1位はガン、2位が心臓の病気、3位が脳の病気、4位が肺炎です。
第5位に位置するのは「不慮の事故」ですが、不慮の事故の中で最も多いのが「窒息」で、交通事故死よりも多いのです。
その理由として、高齢になり、舌の筋肉が衰えると飲み込みが悪くなり、結果として誤嚥を引き起こし、気管に食べ物を詰まらせて、窒息を起こすのです。
ぜひ時間があるときに、舌で上顎を持ち上げるように緊張させる運動(舌の筋トレ)をしましょう。
また、唾液が少なくてお困りの人は「舌マッサージ」がおすすめです。
①うがいをして口の中を湿らせる。
②口腔用の保湿ジェルを指につけて、舌の表面をくまなく蛇行させて、刺激するようにゆっくりマッサージする。
③口の天井(口蓋部)や舌の下の部分、頬の粘膜もマッサージする。
これを1か月続けると、舌下腺、顎下腺、エブネル腺といった唾液腺が刺激され、舌はツヤツヤに若返り、唾液もよく出て、消化も良くなり、口臭が減り、味覚異常や舌の痛みなどが劇的に改善する人が多いのです。
<参考文献>
医者が患者に教えない病気の真実
(幻冬舎・2013)
著者:江田証
(きばこ酵素風呂) 2024年2月26日 12:08
痩せている方がガンになりやすい?
今回は「痩せている方がガンになりやすい?」というテーマです。
「太っていることは病気の危険性が増える」と皆さん認識していますが、日本人は逆に痩せている方がガンになりやすいというデータがあります。
BMI(肥満指数:身長の二乗に対する体重の比で体格を表す指数)とガンによる死亡率のデータを見ると、BMI25ぐらいの方が1番ガンになりにくいようです。
つまり、肥満ギリギリくらいが1番ガンのリスクが少ないということです。
BMIが30を超えて、かなり太ってくるとガンのリスクは上昇しますが、それよりもBMI14〜21くらいの人の方がガンのリスクが高いのです。
<参考>BMIと肥満の判定
◎BMI18.5未満:低体重
◎BMI18.5〜25:普通体重
◎BMI25〜30:肥満1度
◎BMI30〜35:肥満2度
◎BMI35〜40:肥満3度
◎BMI40以上:肥満4度
また、女性は「若いとき痩せていて、中年以降に太る女性が乳ガンになりやすい」ということがわかっており、若いときにダイエットし過ぎると、乳ガンになりやすいので要注意です。
<参考文献>
医者が患者に教えない病気の真実
(幻冬舎・2013)
著者:江田証
(きばこ酵素風呂) 2024年2月19日 12:08
40歳以上の女性は、ウォーキングと筋肉強化で健康寿命が延びる
「ロコモ」のお話です。
正式名称「ロコモティブ・シンドローム」、これはサルコペニアと言い、筋肉が弱くなって、減ってしまっている状態を指します。
サルコ=筋肉
ペニア=減弱、弱くなる
という意味です。
実はロコモが現代人にとって、大きな問題になっており、日本人の40歳以上の女性に筋肉が少ない人が増えているのです。
なぜなら、日常の運動不足などにより、筋肉が著しく減ってきているからです。
そして、今の日本の女性を調べてみると肥満者が減っています。
これは、ダイエットや体型を気にするあまりに、ろくなものを食べておらず、カルシウムやタンパク質などの栄養素も不十分であるためです。
それに対して、男性はメタボが増えているという現状です。
そうすると、今後予想される由々しきシナリオとしては、奥さんの長寿者は増えるが、栄養不足で認知症や筋肉不足から寝たきりになり、旦那さんはメタボで早く死ぬ。
よって、奥さんはひとりぼっちの要介護状態になってしまう。
つまり、女性は長生きはするが、健康寿命が短くなってしまうということです。
よって、私たち人間は運動不足ではいけないということです。
そのために、運動器官の機能上昇のため(ロコモ予防のため)の努力をしなくてはなりません。
若い頃からよく歩くことと、マイルドな足腰の筋肉トレーニングに勤しむ必要があります。
40〜50歳からの努力が、後になって効いてきます。
若い頃からのリスクマネジメントが大切なのです。
<参考文献>
医者が患者に教えない病気の真実
(幻冬舎・2013)
著者:江田証
(きばこ酵素風呂) 2024年2月12日 08:26
体温が高い人は、抗酸化物質を摂る
体温が高いということは非常に良いことですが、その反面として「活性酸素」を生じやすいので、対策として抗酸化物質をよく摂ることが重要です。
<抗酸化物質が含まれる食品>
●ビタミンC、ビタミンE、ビタミンA:新鮮な野菜と果物など
●アスタキサンチン:鮭や蟹、蝦の赤い成分
●リコピン:トマト、人参など
●クルクミン:カレー
●レスベラトロール:ぶどう、赤ワイン、レーズンなど
●スルフォラファン:ブロッコリー
●EPA・DHA:鯖、鰯、鮭、鰊など
そして、<活性酸素吸収能力の高い食品>として、麹、ココア、ドライフルーツ、シナモン、レーズン、玄米、チョコレート、バジルなどが有名です。
<参考文献>
医者が患者に教えない病気の真実
(幻冬舎・2013)
著者:江田証
(きばこ酵素風呂) 2024年2月 6日 10:30
肥満は感染する⁉︎
研究データより、興味深いことがあります。
「Science」誌に2010年に掲載された論文によると、腸の中に細菌を持たない無菌マウスを太っているマウスと一緒に飼うと、太っているマウスの中の腸内細菌が無菌マウスの腸の中に感染し、著しい肥満になることがわかったのです。
太ったマウスの腸の中の特徴は「ファーミキューティス属」の腸内細菌が多いことです。
それに対して、痩せたマウスの腸には「バクテロイデス属」という腸内細菌が多いのです。
腸内細菌の種類が肥満の要因になることを示した最初の論文でした。
もしかすると、太った家系の人は家族から太る腸内細菌を移されていることが将来わかるようになるかもしれません。
現在、腸内細菌の遺伝子ゲノム解析により、肥満を起こす有望菌種116種類が同定されています。
太っている人の腸内に多い「ファーミキューティス属」の菌は、食べたものを過剰に消化し過ぎた結果、食べ物から栄養を吸収し過ぎてしまうことが最近の研究でわかってきました。
それに対して、スリムな人に多い「バクテロイデス属」の菌は、過剰に栄養を吸収しないので、痩せやすい体質にしてくれるのです。
このように痩せている人の腸の中に住んでいる腸内細菌と、太っている人の腸の中に住んでいる腸内細菌では、個体差があります。
<参考文献>
医者が患者に教えない病気の真実
(幻冬舎・2013)
著者:江田証
(きばこ酵素風呂) 2024年1月29日 12:48
ダイエットには運動しながら、鮭を食べよ⁉︎
運動をすると、エネルギーを得るために何かを燃やすわけですが、筋肉などのタンパク質が燃えないで、出来れば脂肪が燃えてくれた方がダイエットに良いわけです。
しかしながら、「なかなか脂肪が減ってくれない」という方も多いでしょう。
そんなときに摂ると良いとされているものが、「アスタキサンチン」なのです。
アスタキサンチンとは鮭や蟹、海老などに含まれる赤い色素の成分であり、抗酸化作用が強く、肌のサビ止めとして化粧品に取り入れられています。
そして、近年の研究データから運動するときに「アスタキサンチン」を摂取すると、脂肪が燃焼しやすいということが明らかになったのです。
アスタキサンチンはメラトニンと同じく、口から摂ると血液脳関門を通過して、脳まで達することがわかっています。
脳に良いことや、目に良いことはわかっていましたが、何とダイエットにも有効なのです。
<参考文献>
医者が患者に教えない病気の真実
(幻冬舎・2013)
著者:江田証
(きばこ酵素風呂) 2024年1月22日 20:36
100件以降の記事はアーカイブからご覧いただけます。